【五節句】5月5日は「端午(たんご)」の節句
公開日:2020年04月28日 最終更新日:2023年10月31日
|
5月5日は「端午(たんご)」の節句です。 菖蒲の節句、男の子の節句ともよばれ、粽(ちまき)や柏餅(かしわもち)を食べて健康を願います。 強い香りを持つ菖蒲を魔除けにした中国の風習が元になっています。 江戸時代に「菖蒲」が「勝負」とつながり、男子の節句とされ、兜や武者人形を飾るようになりました。 |
|
<粽(ちまき)> 笹の葉でもち米を包み、いぐさで縛って蒸したり茹でたりしたものです。 昔は茅(ちがや)の葉で包んだことが名前の由来とされます。 |
|
<柏餅(かしわもち)> 平たく丸めた上新粉の餅をふたつに折り、中に小豆や味噌のあんをはさんで、それを柏の葉で包んだ菓子です。 柏の葉は新芽が育つまで古い葉が落ちないことから「子孫繁栄」を願って、端午の節句の供物として用いられてきました。 ★五節句とは★ |
|
1月7日:人日(じんじつ) [七草の節句] 1年間の無事を祈り、七草粥を食べる 3月3日:上巳(じょうし) [桃の節句、ひな祭り] 邪気をはらうヨモギ入りの草餅を食べる 5月5日:端午(たんご) [菖蒲の節句] 粽(ちまき)や柏餅を食べて健康を願う 7月7日:七夕(しちせき) [七夕祭り、星祭] 索餅(さくぺい)と呼ばれる細い麺で無病を祈願 9月9日:重陽(ちょうよう) [菊の節句] 菊酒を飲んで不老不死を願う 奈良時代から平安時代にかけて中国からもたらされた風俗や暦法を日本固有の行事と習合させたもので、中国の重日(奇数が重なる月日)の考え方によるものである。 いずれも身についたけがれを払う厄払いの行事で、ご馳走をつくって神に供え(神霊に供物を供える日として「節供」ともあらわされる)人々が集い神と共に食事をする、いわゆる神人共食の特別の日のことである。 節というのは季節のことで、その季節のかわり目を節日といい、新しく迎える月日を無事に過ごせるようにと願うところから、いろいろな行事が生まれた。 宮中で行われていた行事が武家社会へ伝えられ、永い日本文化の流れの中で庶民の生活のサイクルとして普及したものである。 |
|
出典:農林水産省Webサイト 「和食文化の保護・継承」 (https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/culture/index.html) |
イメージ
| イメージ画像1 |  |
|---|---|
| イメージ画像2 | 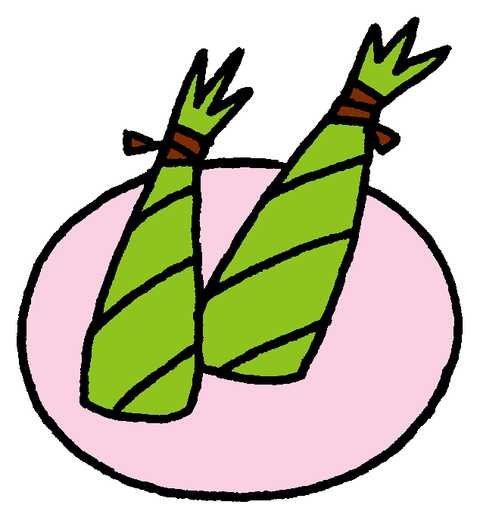 |
| イメージ画像3 |  |